音楽に看取られて
(1)メアリの場合
私が出会った3人の患者さんについてお話しましょう。 最初の患者さんは、私ではなく同僚のローラが担当した方です。ローラはオレゴン州の大きな病院で働いています。あるとき、ローラは女性の患者さん―ここでは仮にメアリと呼んでおきましょう―のために演奏するよう頼まれました。メアリは深い昏睡状態にあり、外部からのいかなる刺激にも反応しませんでした。死期は間近いと思われていました。ローラは彼女のために1時間ほど演奏し、「もう長くはないのではないかしら」と思いながらそこを去りました。
数日後ハープを抱えて病院の廊下を歩いていたローラは、誰かが「ローラ、ローラ」と呼ぶ声を耳にしました。声のするほうに行ってみたところ、驚いたことにそこにいたのはメアリでした。メアリは死んではいなかったのです。しかも意識があり、話すことも辻褄が合っているではありませんか。メアリはローラにこう言いました。(ここでどうか思い出してください、メアリは深い昏睡状態にあって、どんな刺激にも反応していなかったことを。)「ローラ、あなたが私の病室を訪れてくれたとき、私はとても恐ろしい場所にいました。ところが、音楽が始まると、いつの間にか私は暖かい、平安な場所に連れて行かれたのです。」
さて、私たちは普通、昏睡状態にあった患者さんからフィードバックを得るなんてことはありません。ですからこれは患者さんの内なる経験を本人から聞くという滅多にない機会となりました。それからというもの、私は病室を訪れるたびに、とくに患者さんに意識がないときは、この、メアリがローラに語った言葉を思い出すようにしています。
著名な精神神経科医、オリバー�・サックスは次のように語っています。「なぜそうなのか、まだ解明されてはいませんが、たとえ脳の機能が広範囲に侵された場合でも、音楽に反応する能力は最後まで残されているのです。ですから、脳卒中、アルツハイマーやその他の認知症によって障害を持つ人でも、ほとんど奇跡としか言いようがないのですが、音楽に反応することがあるのです。」
(2)ある仏教徒の女性
次にご紹介する患者さんは、35歳になる仏教徒の女性です。彼女は末期癌患者でした。2人いたお子さんはまだ小さかったので、自分がやがて死ぬということを認めようとしませんでした。その点は彼女のご主人も同様でした。しかし、彼女は確実に死に向かっていました。友人たちの依頼で私は彼女を訪れることになったのですが、最初に彼女のお部屋に入ったとき、いったいその音楽は何のための音楽かと尋ねられました。まさか末期の患者さんのための音楽だなどと言えるわけもなく、私は思わず「これは私たちの心の中の霊的な動きと、身体的な動きを喩えた音楽なんですよ」と答えたのでした。彼女が肯いたので、私は演奏を始めました。
最初の曲はケルトの子守唄でした。音楽が始まるやいなや、彼女は涙を流し始めました。ちょっと刺激が強かったかもしれないと心配になった私は、他の曲に変えて、1時間ほど演奏を続けました。ちょうど終わった頃、ご主人が息子さんたちを連れて部屋にやってきて、こう言いました。「こんなに平安な顔をしたあなたを見たことがないよ。」するとその若いお母さんは私に向かって「ありがとうございます、ありがとうございます。手術後、初めて泣くことができました」と言ったのです。それで私は理解しました。彼女が流した涙は、洗い流し、清め、浄化する涙だったということを。彼女から、また来てほしいと言われ、実際、あとで彼女の夫からも、毎日来てもらえないかと電話で頼まれました。
そこで月曜日に再び彼女の病室を訪れました。ちょうどそのとき、彼女は二人の息子さんたちに別れの挨拶をしていたところでした。激しい痛みに加え、肺の働きも弱っていた彼女は、その晩からモルヒネを使う決心をしていたのです。きっとひどく落ち込んでいるのじゃないかと思って部屋に入ったのですが、私の予想に反して、彼女は輝いていました。私を見るなり、彼女はこういいました。「やっと受け入れる覚悟ができました。今は平安です。」
私は彼女のために演奏しました。演奏を終えると、彼女は私に言いました。「あなたの奏でる音楽のおかげでこの[死ぬという]ことが違ったものに感じられました。明日また来てくださいね。」この素晴しい女性はその8時間後に亡くなりました。
彼女の葬儀の後、遺族(夫、妹、母親)と友人たちが彼女の言葉を伝えてくれました。音楽が始まって15分ほどしたとき、痛みが去り、その状態は演奏終了後、およそ1時間続いたそうです。
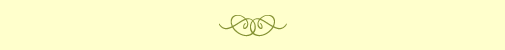
最近、私は隅田川の近く、ホームレスの多いことで知られる山谷地区にあるホスピス「きぼうのいえ」に定期的に通っています。そこで内田さん(仮名)という男性に10回ほど演奏して差し上げました。彼には家族がいませんでした。最初にお会いしたとき、私は自己紹介をしたあと「これから演奏する音楽は内田さんのためだけのものです。他の誰のためでもありません」と言いました。すると内田さんの目に涙が浮かびました。演奏が終わると、内田さんは英語で一言、「サンキュー」と言いました。
内田さんはその後、亡くなりました。亡くなった後、聞いた話では、内田さんは臨終前に洗礼を受ける決心をなさったそうです。洗礼名はパウロでした。ホスピスの職員の方が私に「内田さんは変わりました。だんだん穏やかになって、最期を迎えられました。あなたの音楽のおかげだと私は思います」とおっしゃいました。私自身は、その言葉が当たっているかどうか、わかりません。しかし音楽にはそのような、人を変える力があると強く信じています。それが4世紀の昔、聖アウグスチヌスが語った言葉の意味ではないでしょうか。「歌う人の歌は2度の祈りに等しい。」
(3)音楽に看取られて 山手八郎さん(享年66歳)

きぼうのいえならではのプログラムに、音楽による看取り、ミュージック・サナトロジーがある。ここではその説明と、それを受けて去っていった山手八郎さん(享年66歳)の話をしよう。ぼくたちの看取りのなかでも、素晴らしい旅立ちだったといえるだろう。
山手さんはスリムな人だった。若いころは細身ながら良い動きをするスポーツ選手だったのかな、と思わせるようなところがある。態度は芳しくないのだけれど、服装のセンスが抜群によく、カジュアルでラフな印象は、かつて都会派の好青年だったのだろうと想像する。
山手さんは近くのNPOが運営する宿泊施設から移ってきた。重い呼吸器の病気で、毎分七リットルの酸素吸入が欠かせなかった。息苦しさのため身体を動かせなくなり、その施設では介護が限界になったためである。
山手さんがきぼうのいえに移ってくる前に、スタッフが宿泊施設に面会に行った。日当たりはよいものの、大きな在宅酸素の機械を置いた三畳間の個室の脇に、不安そうな顔をした山手さんは座っていた。
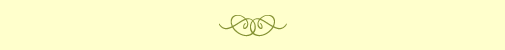
「わたしたちは、これから山手さんが来られるきぼうのいえのスタッフで、ぼくはそこの責任者です」というと、彼はぼくの目を見据えて、しっかりした口調でいった。
「わたしの面倒をきちんと見てくれるんでしょうね!」
「責任者として約束しましょう」とぼくはこたえた。
きぼうのいえへきてからの山手さんの特徴は不満の多さだった。
「ご飯がさめている、温めてこい!」
真夜中に外出しようとして、安全上の問題から「朝になってからにしましょう」というと怒る。そして口ぐせのように「訴えてやる」という。いいがかりに近いものもあった。
「ここにきてから眠れない。あんたたちがちゃんとやってくれないから眠れない。ここにいると病気が悪くなる!」
「そうですね、山手さんにはきぼうのいえのような施設は向かないのかもしれませんね」と美恵さん。
「それはどういうことだ?」
「山手さんはいろいろとご不満がおありのようですから、きぼうのいえよりも病院のように二十四時間、看護師さんが面倒を見てくれるようなところのほうがよいのかもしれませんね」
「病院はダメだ! 看護師なんてろくな者じゃない、あんたのようにそうやってひとを否定することから始めるんだ!」
「否定をしているのは山手さんで、私のは否定じゃありません。山手さん、身体が苦しくて、私たちにあたるのはわかります。お気の毒だと思います。でも、そうやって朝から晩まで人にあたり散らして、はずかしくありませんか? 私は山手さんと話してして腹が立ちます! そうやって不満ばかりいうのではなく、感謝することも学んだほうがいいと思います!」
「・・・・」
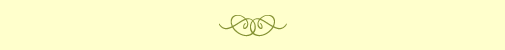

その翌日、二年前からきぼのいえで音楽による看取りをしてくれている、サック・キャロルさんが事務所にきていった。
「今日はどなたにミュージック・サナトロジーをしましょうか」
美恵さんは山手さんを選んだ。
「難しい方ですが、もしかしたらお部屋にも入れさせてもらえないかもしれませんが、ぜひ山手さんをお願いしたいのです。彼は病気に疲れはてています」
そしてその結果に驚かされたのだった。
「山手さんが部屋で泣きました」と、キャロルさんが感動した面持ちで報告してきたのだ。
ミュージック・サナトロジーは、死に臨んだひとの精神的、肉体的な苦痛を音楽で慰め、安らかにあの世に送り届ける営みである。その源は十一世紀のフランスの修道院にまでさかのぼる。ハープと歌声による生演奏で、居室内で一対一で行われ、ハープのたいへん優しい音色と歌声とで、聞き手の身体的、精神的、スピリチュアルな状態を感じ取りながら、愛と注意深いケアの姿勢で演奏される。
山手さんはキャロルさに、「こんな穏やかな気持ちになれたのははじめてだ」といって号泣したという。
ぼくは少し意地の悪い見方をしていた。音楽を一回聞いたくらいで、人間がそうたやすく変わるものではなく、今回、こんな反応があったとしても、次回にはいつもの山手さんに戻るだろうとタカをくくっていたのだった。
だがほんとうに山手さんは変わってしまった。
部屋にようすを見にいって、「なにか困ったことはない?」と聞くと、「そんなになんども見にこなくても大丈夫だよ」といったり、「お茶をいれてこようか」というと、「そんなに甘やかしちゃダメだよ」という。
「ぼくはもう怒るのはやめたんだ、怒るのにはもう疲れたんだ」といい、そしてなんども「ありがとう」というようになったのである。
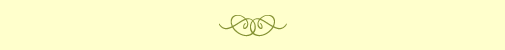
そして底冷えの厳しい冬の夜。山手さんは寝る前にビデオを事務所で借りていった。『鉄道員(てつどういん)』『ハチ公物語』『お墓がない』の三本である。
夜中の十二時、『ハチ公物語』を見ているのを、夜勤のスタッフが確認している。
朝、七時五十分、ぼくの部屋の内線電話が鳴った。夜勤の伊瀬聖子さんだった。
「山手さんがお亡くなりになっています」
部屋にいくと、彼は窓際で、避難ばしごの箱に腰掛けた姿勢で亡くなっていた。
ぼくたちの勝手な想像だけれど、『ハチ公物語』を見ていて涙ぐんだ山手さんは、呼吸が苦しくなって、冷えた外気を吸って呼吸を整えようと、窓際にいって夜空でも眺めていたとき、その時がきたのではないか。特別に満月の美しい晩だった。そして山手さんの顔はとても優しく、少し笑っているかのようにみえた。
それは、彼がひととの交わりを回復させ、感謝することを知ったあとに訪れた幸福な死であったと思う。ぼくは山手さんがもう少し長く、きぼうのいえで幸福感を味わって過ごすことができたらもっとよかったのにと思っている。
冥福を祈りたい。
山谷でホスピス始めました。(山本雅基 著:実業之日本社 刊)

